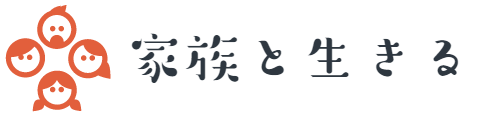親の老後について子供の干渉が少なくなっている
近年、子供をとりまく事情として、「生産財」から「消費財」へと変化したという点が挙げられます。
「生産財」「消費財」・・・聞きなれない言葉かもしれませんね。
ここで、この「生産財」「消費財」について、少し解説をしてみたいと思います。
少し前まで、子供は「生産財」という呼ばれ方をしていたのです。
これは、「子供は大きくなったら親の面倒をみる」ということが期待できた為です。
確かに、昭和の時代ごろまでは、長男は家に残って両親の面倒を見るということが一般的でした。
また、女性も長男と結婚した場合は夫の両親と同居し、家事育児をこなしながら、将来的には夫の両親の面倒をみるというのが当たり前だったのです。
それが、今は「親は子供に迷惑をかけないように自立すること、老後も子供には頼らない生活をすること」を念頭においている家族が増えました。
この考えは、子供世代だけでなく、親世代にも浸透しています。
社会福祉がある程度充実してきたことや、親の面倒を見ることで背負う子ども自身の負担を考えると、「子供に頼りたくない」という親が増加するのも、ちょっと解る様な気がします。
子どもに依存しない関係
そして、子供は「生産財」から、「子供と一緒にいることが幸せだ」「子育てが楽しい」という考えの延長線にある「消費財」という考え方へと移行したのです。
子供に将来の安定を求めるのではない。
子供は育ったら自分たちから自立し、羽ばたいていくものである。
そんな考えが、大半を占めるようになっているのです。
この考え方は、そのまま「核家族化」などへとつながっているのかもしれません。
親は親、子供は子供。
それぞれがそれぞれの生き方を尊重しあい、大切にすることができる様になったことは、子供の人生にとってとてもいいことでしょう。
しかし、反面「子供も親に頼らない生活」を実現するためには、たくさん貯蓄をして将来に備えるなどの準備が必要になりますし、本当に困ったことがあっても、「迷惑をかけたくない」という気持ちが先行するあまり頼ることができないなど、プレッシャーにもなっている様です。
経済が及ぼす影響
バブル全盛期ならともかく、お給料も右肩上がりとはいえない現代では、老後の資金をためるのは至難の業です。
親のハードルは、どんどん上がっているといわざるを得ません。
この為か、近年は「子供を産まない」という選択をする夫婦も増えてきました。
子供を育てるにもお金がかかる、けれど将来老後の面倒を見てもらえるわけではない・・・という現実が、「子供を持たない」という選択をさせているのでしょう。